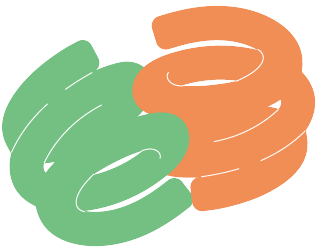てつがく対話2025 in 気仙沼
日程:2025年10月19日(日)、20日(月)
主催:日本学術振興会・受託研究課題「身体性を通じた社会的分断の超克と多様性の実現」(代表:床呂郁哉)クラスターC「身体的実践を通じた分断超克の手法構築」: 立教大学 河野哲也
共催:気仙沼市教育委員会、リアス・アーク美術館、ESD研究所
東日本大震災を経て、東北三陸地域には深刻な人口減少が生じ、世代間、地域に代々住む住民と新規住民との間の乖離が生じ、地域に分断が生じぬように地域コミュニティの再形成・再構築が求められている。この問題を解決する端緒として、気仙沼市の中央公⺠館と市教育委員会と連携し、対話の文化を根付かせるための教育実践・研究活動を実施した。地域外の参加者も含めた多様な視点をもとにして、地域の文化施設を中核としたコミュニティ形成の意義を地域住⺠が見出し、対面での対話の文化の情勢が地域での生活を豊かにし、分断ではなく、よりインクルーシブな社会を志向するきっかけづくりを行った。
具体的には、リアス・アーク美術館において多世代が参加できるイベントを通して、美術の感性的・身体的な経験をもとに哲学対話を行い、美術や⺠俗と自分との関係や地域における文化施設の意義を刷新する機会をつくる。また、気仙沼小学校では、子どもの問いからはじまる哲学対話を実施し、身体を向き合わせた対面性を重視した対話の場づくりの方法と影響について考察する機会を作った。
(1)てつがく対話2025 in 気仙沼
日時:10月19日(日)13:00~16:30
場所:リアス・アーク美術館
参加者計18名:一般参加者6名+市職員3名+美術館館長1名+本出張参加者8名
実践の記録:事前にリアス・アーク美術館の館内を自由に見学したうえで、その感性的な体験を言語化しながら、対話の場が始まった。まず、門田岳久教授(立教大学)、山内宏泰館長(リアス・アーク美術館)、村上滋郎先生(東北芸術工科大学)から、それぞれ10分程度、話題提供がなされた。
主に、門田教授からは民俗学における「はなし」の重要性、山内館長からはリアス・アーク美術館の特徴や民俗と美術館の接点、村上先生からは地域における美術の可能性について述べられた。その後休憩をはさみ、河野哲也先生(立教大学)から企画の趣旨や哲学対話の方法についての説明があったのち、参加者から自由にテーマや問いが出された。参加者からは、豊かさとはなにか、時間に対しどう抗うことができるか、風景とはなにか、などが出された。一般参加者や美術の専門家、学生や研究者などさまざまな立場から風景を描くことや残すことについての対話が重ねられた。参加者同士の対話は、気仙沼の風景を描くこと、残すことと伝えることについての話題に展開し、時間となり、終了した。
(2)気仙沼小学校における哲学対話実践
日時:2025年10月20日(月)9時35分~11時25分
場所:気仙沼小学校
対象:4年生(35名)、6年生(40名)
授業のねらい・目標:他者と対面で向かい合い、コミュニケーションをして、多様な考え方や価値観に触れ、他者との違いを理解し、尊重する態度を養う。児童が、日常の「なぜ?」「どうして?」といった疑問を「問い」として立てる力を育む。
実践の結果:各学年とも、哲学対話の説明と約束事を確認したのち、「なんで?」「どうして?」と感じることから問い出しを行った。その中から多数決で一つの問いが選ばれた。4年生は「なぜ星座に名前があるの?」6年1組は「なぜ学校に行かなきゃいけないの?」6年2組は「なぜ信号は赤青黄色なの?」であった。各学年とも10名程度のグループに分かれて対話を行った。