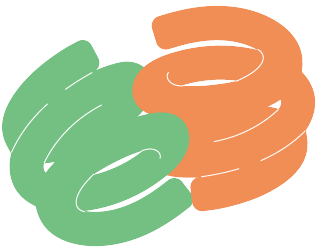JSPS身体性課題 24年度年次研究集会
JSPS学術知共創プログラム「身体性を通じた社会的分断の超克と多様性の実現」2024年度年次研究集会を、下記のように本課題の分担者・参加者による進捗報告と今後の研究計画の打合せを実施した。
後半は異分野融合型若手育成セミナーを実施して本課題の研究員である大村優介氏の研究と論文執筆構想に関する発表と討議を実施した。
日時:2024/10/20(日)14:00-18:30
場所:東京外国語大学AA研304号室
内容:14:00-17:40 分担者・参画者による進捗報告&討議
17:40-18:30 異分野融合型若手育成セミナー
内容の詳細は以下の通り。
床呂郁哉(研究代表者:東京外国語大学AA研)
年次研究集会の趣旨説明及び2024年度の本課題の実績などをまとめて報告。あわせて自身の研究課題の進捗(ポピュラー文化を通じた民族間境界の越境)などについても説明がなされた。
吉田ゆか子(クラスターA:東京外国語大学AA研)
2023年11月から12月にかけて行われた「バリの伝統芸能における身体性に関するアウトリーチ・イベント」を振り返りかえった。そしてその背景や、実施後の現地の人々の反応などを報告し、その意義や、準備から実施に至るまでの過程で得た発見などについても報告した。
村津蘭(クラスターA:東京外国語大学AA研)
2024年1月に行われた「アカデミックリサーチと芸術の未来」及び2023年11月「ワークショップ「日常をフィールドワークする①、②」」の報告及び、今後実施予定のイベントついても報告がなされた。
山口真美(クラスターB:中央大学文学部)
今年度の研究に関する進捗報告及び、本課題の協力イベント「たんけんしよう! あなたの知らない”かお”の世界」の報告及び、今後予定されているイベントについても情報共有をいただく。
工藤和俊(クラスターB:東京大学大学院総合文化研究科)
スポーツに携わる立場から本課題の研究を進める過程において、2024年8月に行われた本課題のバリ島での学術集会の参加をきっかけにスポーツの位置づけについてあらためて考える必要を感じたことが説明された。また、スポーツを通した国際化や人々の協調について、社会的分断の超克を実践したネルソン・マンデラ氏の功績等に関連付けて考察され、さらにスポーツビジネスの巨大化に伴って生じる社会的弊害の可能性について報告された。
河野哲也(クラスターC:立教大学文学部)
2024年に沖縄の学校や美術館で実施した哲学対話のイベントや、タイ・メーチャン村やバンコクで行ったスタディーツアーなどについて報告がなされた。
小手川正二郎(クラスターC:國學院大学文学部哲学科)
2024年7月13日に東京外国語大学にて行われた「ルワンダの戦前と戦後―国の変化を共に見る」のイベント報告及び自身の研究に関する進捗報告がなされた。
大村優介(研究員:東京外国語大学AA研)
「ラオス首都ビエンチャンに生きる個による、表現としての生の民族誌」と題した自身の研究内容進捗及び自己紹介がなされた。各参加者からフィードバックがなされた。
その他の研究分担者、参画者の進捗報告については以下の通り。
高橋康介(クラスターA:立命館大学総合心理学部)
東アジア圏における分断と超克の実践に関し、2024年2月に台湾の国立成功大学(National Cheng Kung University)からChun-Chia Kung教授を招聘し、日本国内での共同フィールドワークの実施、および国際シンポジウム “Workshop on Cross-Cultural and Individual Perspectives in Face and Body Perception”を開催した。
2024年度以降は身体実践に根付いた社会的分断の超克と多様性の実現にいたる実証的研究としてオンライン実験手法により研究を進めている。
2024年9月にはケニア・ナイロビのケニヤッタ大学で開催された8th International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sports and Dance Africa Regional Congress 2024 (ICHPER.SD)にオンライン参加を行い、シンポジウムの企画および「Beyond Boundaries: A New Approach to Exploring the Diversity of the Physical, Mental, and Conceptual Body」というタイトルで研究発表を行った。これらの活動を通して、アフリカ地域における恒常的な調査・実験研究の実施体制の構築を進めている。
渡邊克巳(クラスターB:早稲田大学理工学術院)
クラスターBでは心理学等の人文系の専門家に加え、更に運動科学や認知科学等の自然科学系にも跨る分野の研究者とも連携して、社会的分断とそのミクロな身体的基盤に関して学際的な理論構築を行っていくことになっており、特に本チームは分断の身体的基盤に関する潜在的過程を含む認知科学的解明を主に分担することになっている。
田中みわ子(クラスターC:東日本国際大学健康福祉学部)
・研究テーマ:障害者の芸術実践を通じた社会的分断の超克の方法論に関する研究
・本研究課題に関して、2024年8月14日から19日にインドネシアのバリ島において、実地調査を実施した。
・別途、同研究分担者である小手川正二郎氏による企画「ルワンダ―の戦前と戦後―国の変化を共に見る」(2024年7月13日於東京外国語大学)においてコメントを担当した。
・次年度に森田かずよ氏によるワークショップの企画を実施する方向(2025年6月を予定)で内容を検討している。
Caitlin Coker(研究参画者:北海道大学大学院文学研究院)
① 札幌で活動する舞踏家・コンテンポラリーダンサーとの研究プロジェクト
研究内容は、ダンサーたちと共に踊り、舞台を踏み、作品を共作するという参与観察の側面、彼女たちの舞台を鑑賞するという観察の側面、さらに聞き取り調査を行う側面があります。
② 石垣島で駐屯地反対運動を率いる女性との研究プロジェクト
今年の9月末に石垣島を訪れ、2023年に石垣島に設置された駐屯地への反対運動を率いている女性に会いました。この方の反対運動について調査を行うことを検討しています。
広瀬浩二郎(研究参画者:国立民族学博物館人類基礎理論研究部)
下記2件について報告がなされた。
2024年10月30日~11月9日「手から始めるアドベンチャー」
2024年9月19日~12月10日「みんぱく創設50周年記念特別展「吟遊詩人の世界」 瞽女(ごぜ)――見えない世界からのメッセージ(日本)」
鳴海拓志(研究参画者:東京大学大学院情報理工学系研究科)
オリィ研究所が運営する分身ロボットカフェでは,身体障害等を抱え外出困難な人々が遠隔操作可能なロボットアバタを使用して就労にあたっている.われわれのこれまでの調査では,パイロット(CAを遠隔操作して就労にあたる者)全員がOriHimeという同一のロボットアバタを用いて活動を行っているため,個々人の身体性が画一化され,それゆえに接客時のコミュニケーションにおいて障害という身体特性を前景化させないことに成功していること,この障害の後景化がそれまで周囲の他者から位置付けられていた自らのアイデンティティ(例:障害者、働けない人)を解体する効果を持ち,障害の位置づけを変容させることで将来に明るい展望を見出させることに寄与していること,一方では自分らしく社会に受け入れられたという感覚が低下することがあることを明らかにしてきた.
対して,最近行った調査では,身体性の違いを後景化させるロボットアバタと,各パイロットの個性を積極的に表現するバーチャルアバタを併用することで,パイロットがそれぞれ自分の望むアイデンティティを社会の中で探索・確立していけるか,そのことにどのような効果があるかを検証した.身体的障害の観点だけでなく,ジェンダー違和を感じる参加者にとっても新たな身体性のもとに行われる現実とは異なる社会的インタラクションが効果的に働くことが示唆され,実験で行ったような活動が障害だけではない多様な分断の超克に資することが示唆されている.こうした結果は,メタバース等を活用して新たな身体性のもとに社会的活動を行えるようにすることが,誰もが自分らしく社会で受け入れられたと感じ,社会の中での自分の役割や位置を見つけていくことに貢献することを示唆するものである
山本芳美(研究参画者:都留文科大学文学部比較文化学科)
2024年5月1日(水)より7月28日(日)まで、京都の私設ミュージアム「おもちゃ映画ミュージアム」で企画展「毛利清二の世界:映画とテレビドラマを彩る刺青展」(略称:「毛利清二の世界展」)を開催した。具体的な成果はこちらよりご覧ください。
丹羽朋子(研究参画者:国際ファッション専門職大学国際ファッション学部)
(1)第177回北陸地区研究懇談会 「能登半島地震と人文学/人類学」連続セミナー第3回「3.11から学ぶ(2) 震災の記録と表現—ドキュメンタリー映画と演劇の制作実践から」
の企画および講演
・日時: 2024年6月22日(土)13:00~16:30
・会場: 金沢大学角間キャンパス 金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」1階研修室
・概要:能登半島地震の支援や研究を行いたい研究者や実践者に向けて、東日本大震災の記録と表現をめぐる実践とそのような活動についてのリサーチ手法等について、自身のレクチャーに加えて、具体的な作品上映や作り手を交えた座談会を合わせたセミナーを企画・実施した。
・プログラム
①丹羽朋子レクチャー「震災の経験を記録することと、表現して伝えることの間」
②菅野結花氏の2作品上映
《きょうを守る》(ドキュメンタリー映画、2011年、70分)
《平行螺旋(スパイラル)》(演劇公演の記録映像、2015年、60分、脚本:こむろこうじ、
制作:劇団もしょこむ)
③座談会「震災の記録と表現の場をひらく」(菅野結花/聞き手:丹羽朋子)
【今後の予定】
(2)展覧会「PART OF THE ANIMAL-動物と人間のあいだ」の展示・ワークショップの共同企画・制作
森田かずよ(研究参画者:NPO法人「ピースポット・ワンフォー」)
2024年9月21日-22日、所属するダンスカンパニーMi-Mi-Bi(みみび)で、豊岡演劇祭で『島ゞノ舞ゝゝ(しまじまのまいまいまい)』を上演。フェスティバルプロデュースとして選出され、ダンサーおよび演出として参加した。マイノリティーな身体や特性を持つアーティストがクリエイションで自らのアイデンティティとどのように向き合うか、引き続き更なる検証を行いたい。
西井凉子(研究参画者)
2024年6月に行われた人類学カフェ「わたしたちは(死んだら)どこへ行くのか − 死とアート」において、死という生きる上で根源的な経験がアートにおいてどのように解釈され、表現されているのを、地主麻衣子さんの像作品上映から考えることにより、死と共に生きている私たちの現実を捉え直す試みを行った。